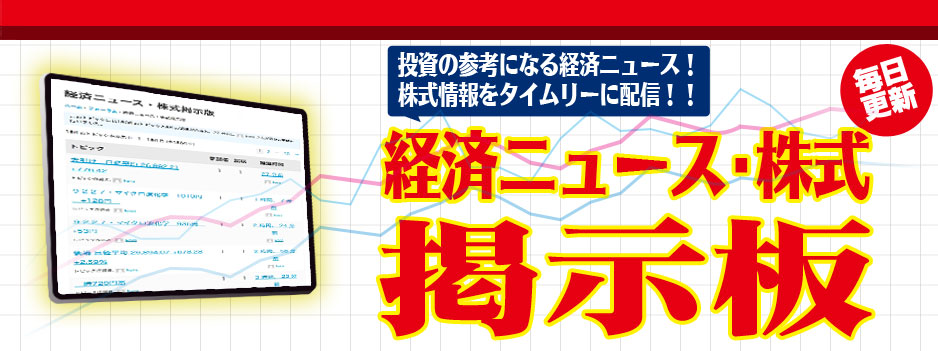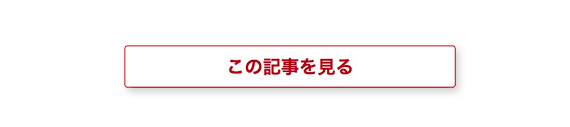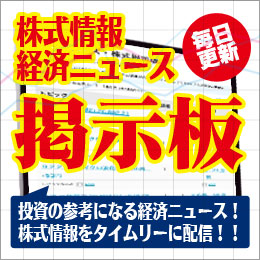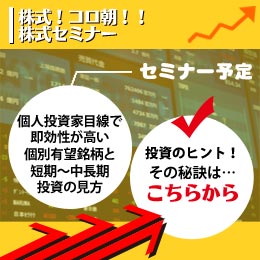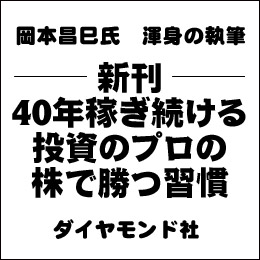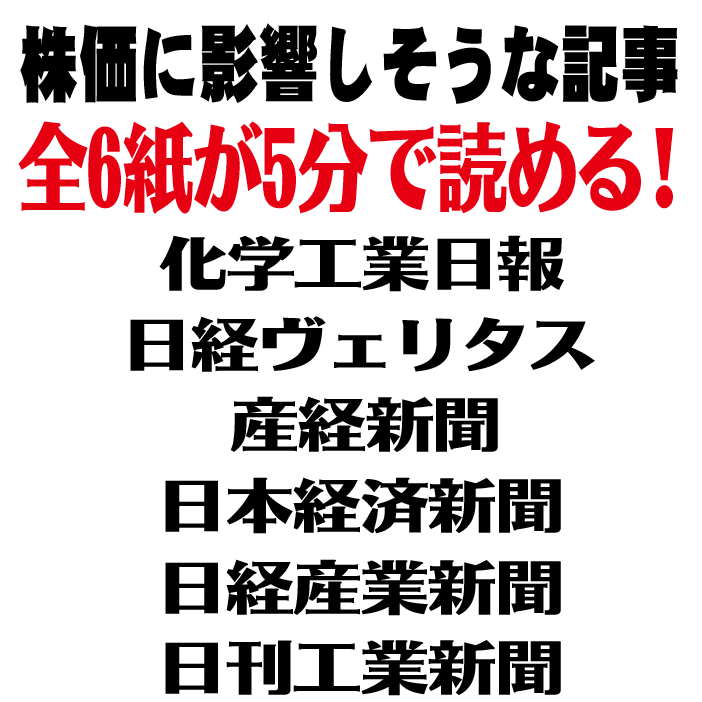
扉を開いて(円安の宴は終わった)
- 2016年04月10日
- 株式投資・経済ニュース全般
2016年4月10日(日)晴れ
・円安の宴は終わった。1ドル100円時代、日本は耐えるか。
3日で3円超の急騰ぶりに「暴力的な円高だ」との悲鳴も上がる。
同日朝には財務省高官も円高けん制。8日には麻生太郎財務相が「場合によっては必要な措置を取る」と述べ、
ようやく上げは一服したが、なお円の先高感は強い。
「アベノミクス相場の円安」を支えた構造に転期迎えている。
1つは金融政策の変化。経済回復背景に2012年後半ごろからドル高を事実上、容認してきた米国。
だが足元で「ドル高是正に向けた動きを強めている」との見方が根強い。
米利上げが遅れ、日米の金利差が広がらない中では円安シナリオは描きづらい。
2つ目は円安要因の1つだった経常収支の赤字が、足元で黒字に変化。
東日本大震災以降、燃料費増が赤字の原因だったが、最近の原油安で赤字が縮小。
加えて訪日客の増加を支えに経常黒字が定着する傾向で円高に振れやすい。
3つ目は需給の変化。昨年までの円安傾向支えた海外投機筋の円売り。
それが最近の円上昇を見て円を買い越す動きに転じ、3月の段階で8年ぶりの買越額記録。
市場では一段の円高阻止へ政府・日銀の円売り介入や追加緩和に期待する声もある。
だが通貨安競争を避ける国際協調の流れは無視できない。
1ドル130円目指すような「円安の宴」は終わり、日本経済、企業の真価が問われる局面に入った。
・円安の宴は終わった。消えた長期円安観測。
円相場、3つの構造転換。アベノミクス支えた条件、逆回転。
1.ドル高是正に米動く。ドル巡る米金融政策の変化。
2008年のリーマン・ショック前後、米連邦準備理事会(FRB)は米経済立て直しと金融危機の回避狙い
大規模な金融緩和を進めてきた。その結果、円が11年には一時1ドル75円台まで上昇。
それが12年後半頃から雇用の増加やシェール革命など米経済の回復が見えてきて、
米政府やFRBはドル高容認に傾いた。
米金利は上昇し、日米金利差は拡大。円売り・ドル買いの流れを生んだ。
だが、足元の情勢は変わった。ドル高で米企業の業績が悪化。
利上げを急げばドル高による米景気下振れに加え、新興国からのマネー流出を加速させかねない。
FRBは再びドル高是正に傾いたようだ。
2.経常収支が黒字転換。日本経済の構造の変化。
10年ごろまで経常収支は年10兆〜20兆円の黒字だった。
それが11年の東日本大震災以降、原油など燃料の輸入が膨らんだ結果、経常黒字は14年まで4兆円前後に縮小。
これが円の下げ圧力として働いていた。
だが最近の原油などの資源安で原材料の輸入額は減少し、貿易赤字は縮小傾向にある。
15年の経常黒字は16兆円まで拡大し、円の上昇圧力となっている。
3.海外勢が円買い拡大。需給要因。
海外勢は低金利の円を売って外貨を買う「円キャリー取引」展開。
12年秋ごろから円下落見込んだ投機筋の円売りポジションかが膨らんだ。
シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の投機筋の通貨先物取引、
円は12年10月に売り越しに転じ、売越額は13年12月に約1兆8000億円まで拡大していた。
それが、中国の市場混乱など背景にリスク回避の円買いで円が上がりやすくなったと見るや、
円を買い戻す動き加速。16年年明け以降買い越しに転じ、円の買越額は3/8で8000億円とほぼ8年ぶりの高水準に。
円相場はこれまで3つの構造的な売り要因で下落してきた。
今度は逆に円高圧力に押される風景へと様変わりした。
・円安の宴は終わった。10人の市場関係者にアンケート。
円安派は「守勢」、10人中6人が年末までにいったん1ドル100円付けると予想。
為替介入や財政出動、消費増税の延期といった対策が効果的に打ち出されれば、
再び円安基調に転じるとの見方も根強い。
・円安の宴は終わった。追い詰められた日銀、苦境見透かす市場。
マイナス金利政策を決める直前の1/29の円相場は1ドル118円台半ば。2カ月余りで10円も円高へ。
2014年10月の追加緩和の時は1カ月で109円から120円台への円安が進んでおり、天地の差。
市場は冷徹、日銀の苦しい事情見透かし、円高止まらず。
4月に追加緩和が見送られれば、投機筋の円買いも加速しかねない。
動かないわけにはいかないが、動くこともできず。4年目迎えた黒田日銀はこれまでになく苦しい立場に。
・円安の宴は終わった。上場企業に減益の足音。
今期1ドル110円想定多く、新興国通貨安も懸念。
アベノミクス相場が本格始動したのは12年から。
その間1ドル80円程度だった円相場は15年夏には125円まで円安に振れ、上場企業の収益を大きく押し上げた。
しかし、2017年3月期は、最近の円高傾向背景に期初の段階から減益決算組む企業も出てきそう。
上場企業全体でも経常減益になる懸念高まっている。
富士重工 <7270> [終値3401.0円]
今期も市場が拡大する北米中心にSUV(多目的スポーツ車)の販売好調見込む。
同社の輸出比率は7割超す。前期着地を1ドル120円程度として、
仮に1ドル110円の水準が続けば営業利益で1000億円の押し下げ要因。
1ドル110円前提とすれば製造業で最も影響は大きいトヨタ <7203> [終値5467円]4000億円程度にのぼる。
・円安の宴は終わった。主要企業の今年度の円高による収益影響。
マイナス トヨタ <7203> [終値5467円]為替影響額(対ドルで1円円高になった場合)400億円
ホンダ <7267> [終値2882.5円]110億円 日産自 <7201> [終値968.4円]110億円
富士重工 <7270> [終値3401.0円]98億円 日立 <6501> [終値474.7円]38億円
三菱重工 <7011> [終値384.5円]20億円 キヤノン <7751> [終値3152.0円]46億円
プラス ソニー <6758> [終値2858.5円]70億円 富士通ゼネ <6755> [終値1768円]3億円
ニトリHD <9843> [終値10380円]16億円
・円安の宴は終わった。投資・消費の下振れ、デフレ脱却に影。
直近の株安の背景には円高による企業業績への期待の低下がある。
日本株の売り越しに転じた海外投資家が最も注目しているのがアナリスト予想の変化。
JPモルガン・アセット・マネジメントの集計、
東証1部上場企業対象にしたアナリストの利益見通しの下方修正は3月405と上方修正の2倍近くに達した。
昨夏までは欧米で下方修正が増える中でも日本は上方修正が優位だった。
だが中国景気不安や円高背景に下方修正が徐々に増加。
一方、米主要企業では2月に上方修正数が190と下方修正の2倍。
円高は企業収益だけfでなく、様々な経路で日本経済に影響及ぼす。
訪日外国人(インバウンド)の失速懸念もその1つ。
最近の株安が企業や消費者のマインドにどんな影響与えるかも焦点。
・先週の日経平均株価は週間で342円(2.1%)下落し、2週続落。8日には一時1万5500円割り込み、
2014年10/31に日銀 <8301> [終値37200円]が追加金融緩和を実施する前の水準(1万5658円)下回った。
15年末から日本株売りを続けている海外勢だけでなく、国内投資家にも先行きに弱気な見方が広がっている。
個人投資家も買い向かうよ料に乏しい。
信用取引で買った株の含み損益度合い示す信用評価損益率は1日申し込み時点で
前の週のマイナス1092%からマイナス13.15%に悪化。
カブドットコム <8703> [終値344円]河合達憲氏は日経レバレッジ <1570> [終値10210円]の動向注視。
昨年11月の上昇局面に日経レバレッジを信用取引で購入した買い残が6カ月後の期日が近づき、
決済の売りが出やすくなるため。「5月中旬に期日迎えるものが多い」という。
変化の兆しが出てきたものの、当面は慎重姿勢が続きそう。
・発掘実力企業:ニッチで稼ぐ(11)アサンテ <6073> [終値1541円]シロアリの防御・駆除で最大手。
農協(JA)との業務提携軸に基盤築いている東日本に加え、これまで手薄だった中国、四国などの
西日本への営業網拡大進めており、2016年3月期の税引き利益、前期比18%増の16億円と過去最高。
シロアリ防除支えるのは約250人の作業員。
業績の伸びを支えている要因には、日本の社会構造の変化も。
少子高齢化の影響で、空き家は増えている。「住宅を少しでも長持ちさせたいと考える人が増え、受注増」と。
・会社がわかる 特集村田製作所 <6981> [終値12835円]自動車、エネルギーなど新市場の開拓を急いでいる。
すべてのモノがインターネットにつながるIoT時代の到来見据え、
無線通信に必要な部品やソフトウエアを一貫して提供できる体制整える。
主力スマートフォン(スマホ)部品の高機能化を支えに引き続き伸ばしつつ、
持続的な成長に向けて新たな収益源を育てる。
・昨年日本株全体の値動きを支えた小売株が昨年とは打って変わって、今年は資金流出が目立っている。
国内消費の伸び悩みへの懸念強く、アパレルや百貨店などで業績の先行きに弱気な声が増えてきているため。
市場では、消費増税の延期など消費下支え策を政府に求める声が強まっている。
小売り株が安い背景には国内消費の鈍化への警戒感。
2月の消費支出は、うるう年で1日多かった分を調整し、物価変動の影響除いた実質で前年同月比1.5%減。
実質では6カ月連続のマイナス。「(14年4月の)消費増税の影響が継続しており、消費者の節約志向が強い」。
「株安による逆資産効果も消費を押し下げている」。
円高の進行で訪日する外国人観光客の消費が鈍るとの懸念も浮上。
5月下旬の主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)に向け、政府の景気対策への期待は高まりやすい。
消費動向に連動する小売り株は特に、政策をにらみながらの展開になる。
・人民元はひとまず安定。8日の対ドル相場は1ドル6.47元台で推移、
1月に付けた安値より1.4〜1.5%ほど元高になった。
外貨準備増も通貨安懸念払しょくできず。
中国が恐れるのは昨夏までのように元がドルに連れ高し、海外に資金が流出する事態。
ドル安というぬるま湯の中では、人民元が危機を脱したか判定するのは難しく。
・OUT Look:今週の株式相場、日経平均株価はいったん戻り試す展開か。
PBR(株価純資産倍率)が1倍に接近するなど割安感は強い。
ヘッジファンドなどによる空売りの買い戻しが入りやすく、短期的に上昇する場面も。
もっとも円相場に左右される展開に変わりなく、市場では1万5500〜1万6500円での推移を予想する声が多い。
東証1部では5割超の銘柄がPBR1倍割れの水準。
日経平均株価の25日移動平均からの下方かい離率は、8日時点で「売られ過ぎ」とされる5%超。
世界的に見て日本株の出遅れも鮮明。昨年末比プラス圏にある米ダウ工業株30種平均に対し、日経平均は17%安。
三菱UFJモルガン・スタンレー藤戸則弘氏は
「介入警戒から為替の動きが落ち着き、今週の株価はいったん持ち直す」と読む。
今月下旬から始まる3月期企業の決算発表通過するまで、日本株は円相場次第ということになる。
・Wall Street:今週の米株式相場は1-3月期米企業の決算発表にらみ神経質な展開か。
先週1週間のダウ工業株30種平均は原油安などで市場心理が冷え込み、1%下落。
足元で原油相場は急反発、原油の動向も引き続き市場参加者の注目集めそう。
11日米非鉄大手アルコア皮切りに、大手米企業の1-3月期の決算発表が本格化。
S&P500種株価指数採用銘柄の収益予想は前年同期比9%の減益見通し。
業種別ではエネルギー株や素材関連企業が減益幅拡大させる要因とみられている。
それだけ市場関係者はアルコアの決算発表注視。13日にはJPモルガン・チェースの決算も発表。
・世界市場往来:先週の世界の株式相場は主要25の株価指数のうち8指数が上昇。
上位1位ベトナム週間騰落率2.49% 2位ロシア1.99% 3位スイス1.68% 4位英国0.95% 5位マレーシア0.46%
下位25位ポーランド▲2.73% 24位メキシコ▲2.61% 23位インド▲2.36% 21位日本▲2.12% 17位米国▲1.21%
(日経ヴェリタス)
———————————————————————–
株式会社アスリーム
INTERNET MEDIA OF INVESTMENT NEWS
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-5
URL : http://koronoasa.com/
———————————————————————–
記事の続きはコロ朝プレミアムで!